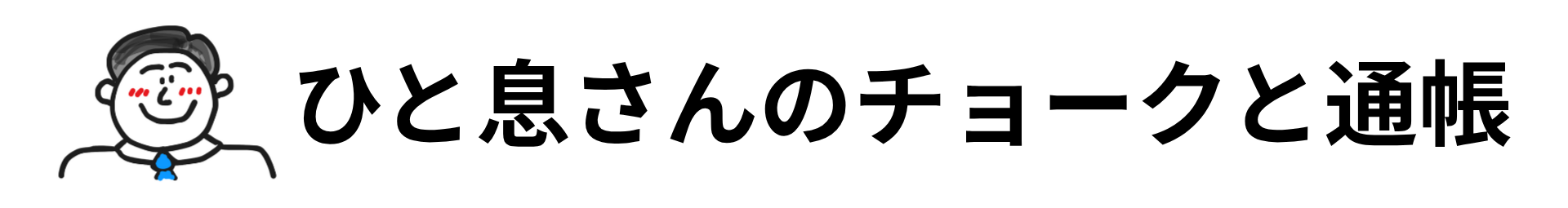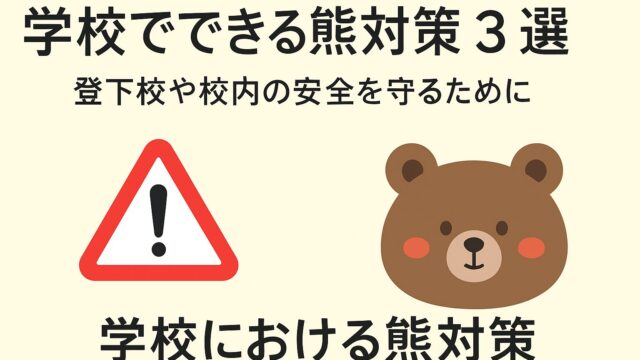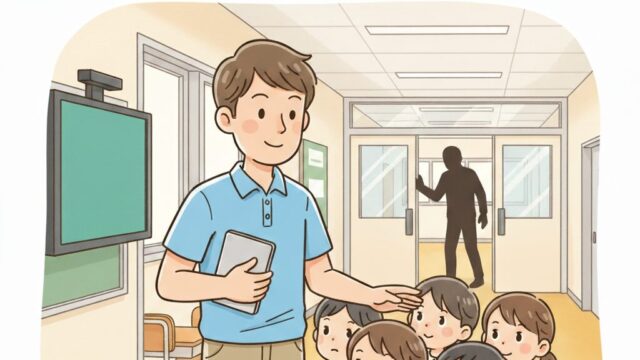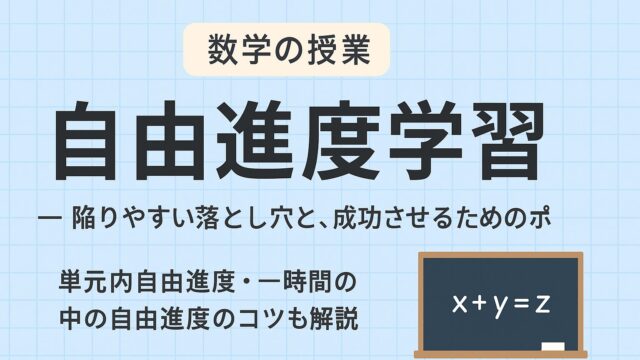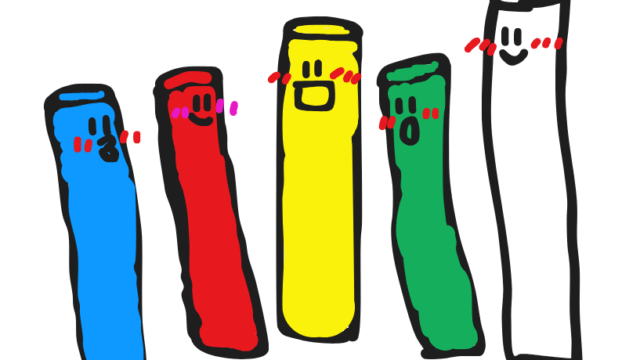教員の多忙化の理由教員の多忙化はなぜ終わらない?現場で感じた3つの理由教員の多忙化の理由
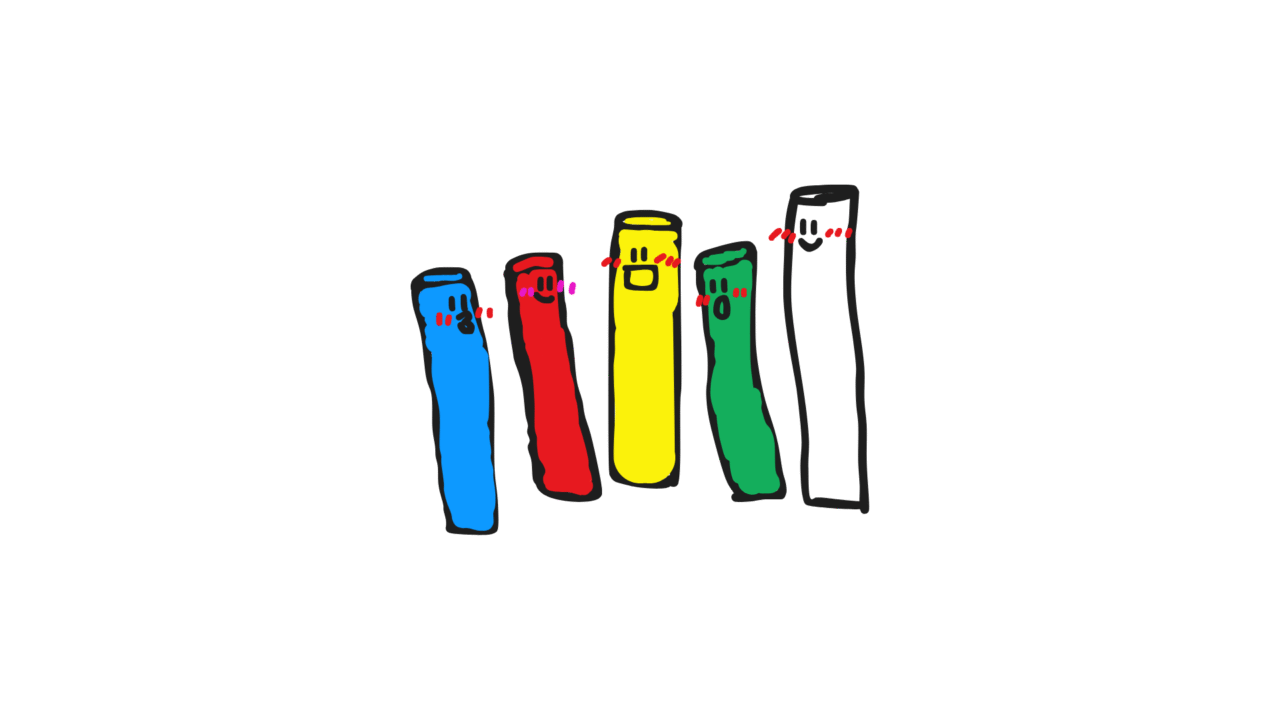
教員の多忙化の理由とは?
私が新採の頃は、毎月120時間の時間外勤務をしていました。
さらに、土日に自宅でテスト作成や授業準備をしていたので、実際には月168時間ほど働いていたと思います。
今では考えられない数字です。
現在でも家で仕事をすることはありますし、テストづくりは一気に仕上げるタイプです。
数学を3学年分担当していたときは、3学年分のテストを一日で作ることもありました。
これは「数研出版のスタディーエイド」というアプリのおかげです(また別の記事で紹介しますね)。
少しずつ働き方改革が進み、業務改善も見られるようになりましたが、それでもなお「多忙だ」と感じる日々です。
では、なぜ教員の多忙化は続いているのでしょうか。
私はその理由を次の3つに整理しています。
教員多忙化の3つの理由
① ベテラン教員の減少と中堅層の薄さ
定年や家庭の事情による退職が続き、ベテラン層が急速に減少しました。
そのポジションを引き継ぐ中堅層が少なく、若手教員に多くの業務が集中するようになっています。
担任業務や学年業務よりも校務分掌が優先され、日中は授業や生徒対応に追われ、ようやく自分の仕事に取りかかれるのは17時以降。
慢性的な多忙化の原因の一つです。
② 生徒一人ひとりの個性を尊重する文化
教育において大切な考え方ですが、対応の多様化によって業務負担が増えています。
落ち着きのない生徒、控えめな生徒、自己主張の強い生徒…。
それぞれに適した対応を求められ、日々の指導がより複雑になっています。
③ 委員会・研究会などの外部業務の増加
自治体によっては、研究会や委員会活動が活発に行われています。
研究授業や資料作成、発表など、さまざまな業務が先生方に割り当てられます。
成長の機会である反面、学校行事や部活動と重なり時間が圧迫されます。
出張後に学校へ戻って仕事を続ける先生も多く、負担が大きいのが現状です。
教員を増やすという選択を
働き方改革を進めるためには、まず教員の増員が必要です。
給料や待遇を改善し、教職を「続けたい」「戻りたい」と思える仕事にすること。
それが、子どもたちにも、そして教育の未来にも、最も確かな投資だと思います。