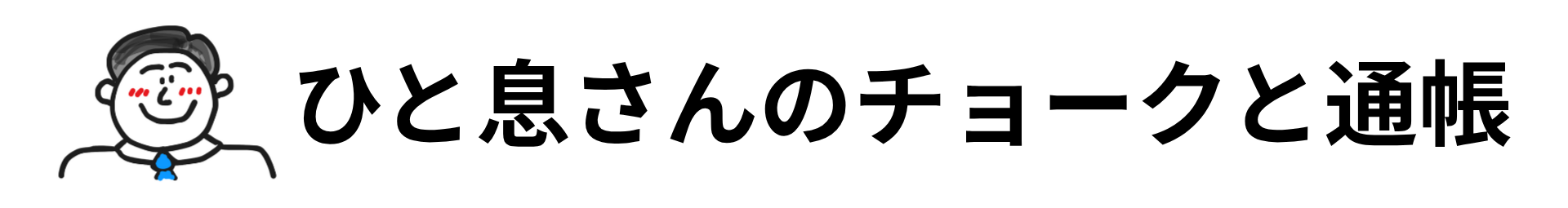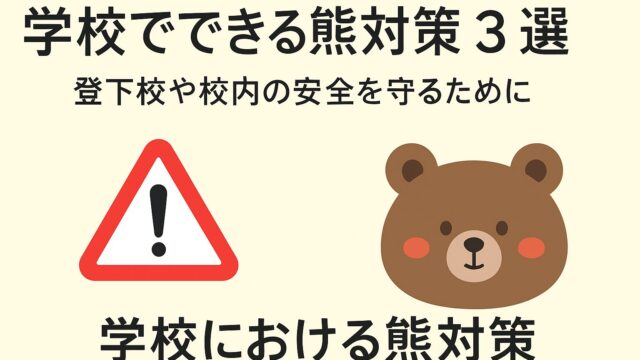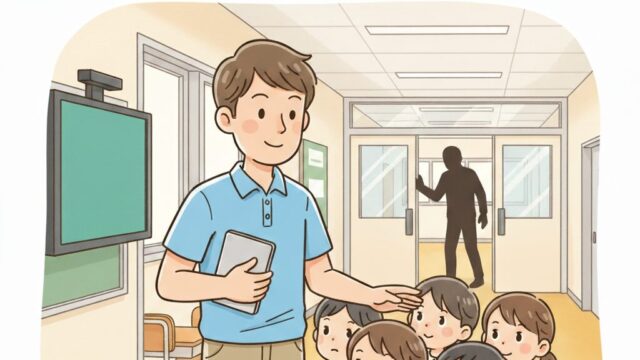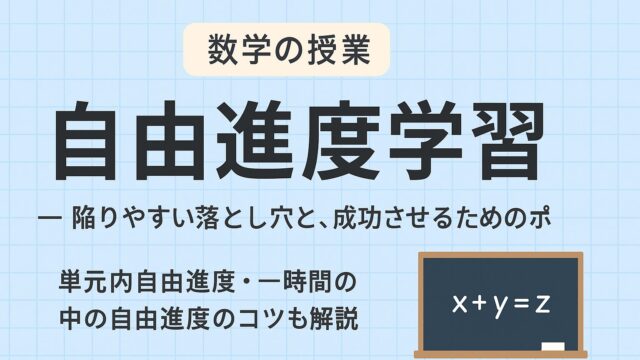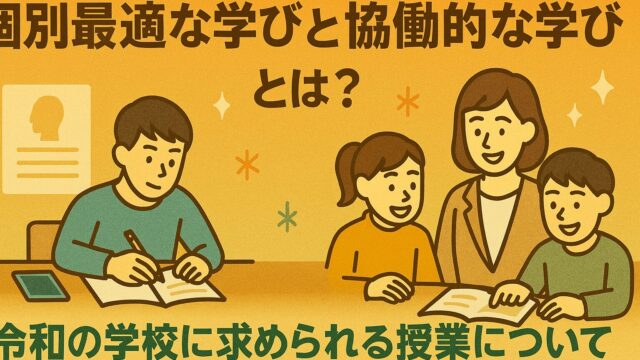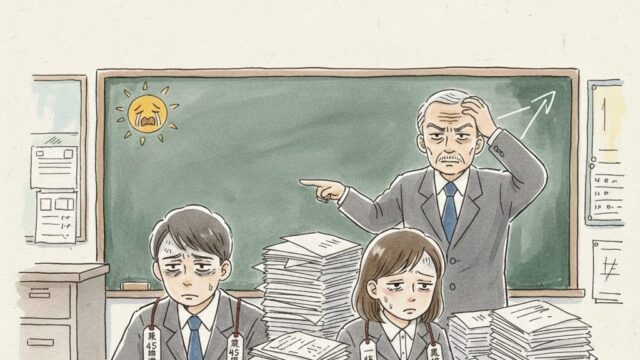チョークさんと通帳さんの放課後トーク:先生の多忙化はなぜ終わらないの?
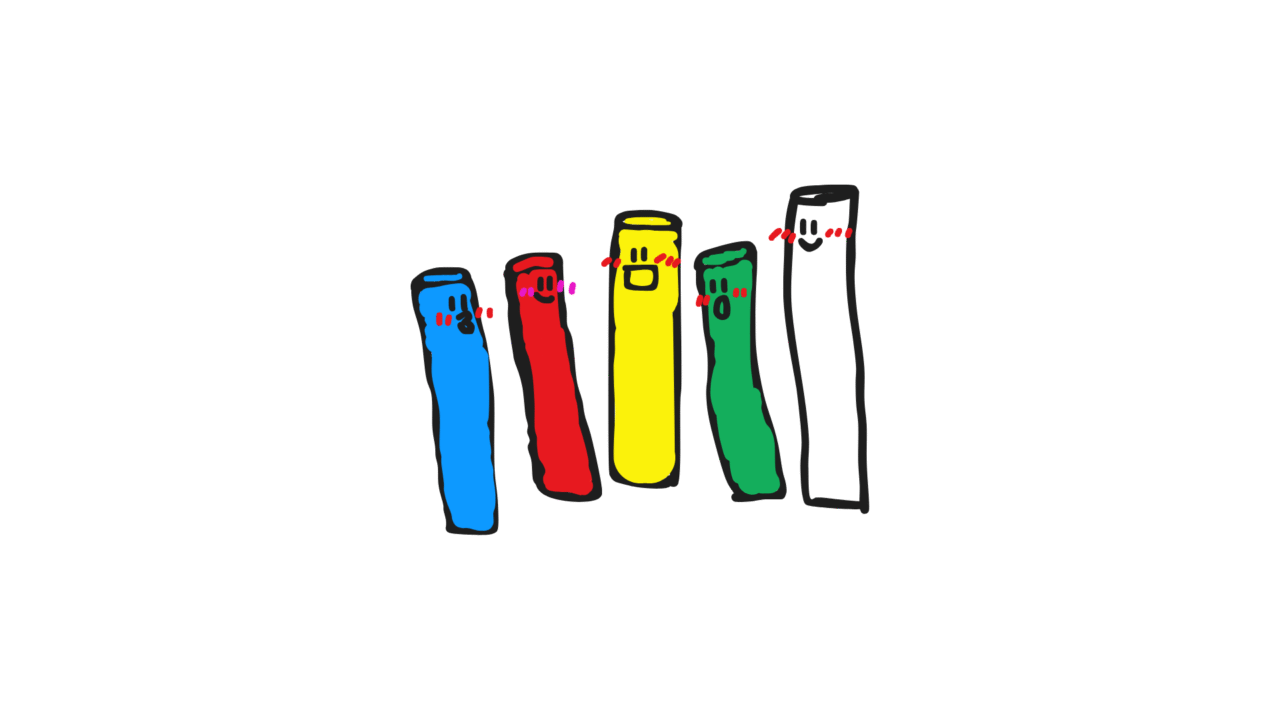
チョークさんと通帳さんの放課後トーク:「教員の多忙化って、なんで終わらないの?」
放課後の職員室。テストの採点を終えたチョークさんが、通帳さんにぼやき始めました。
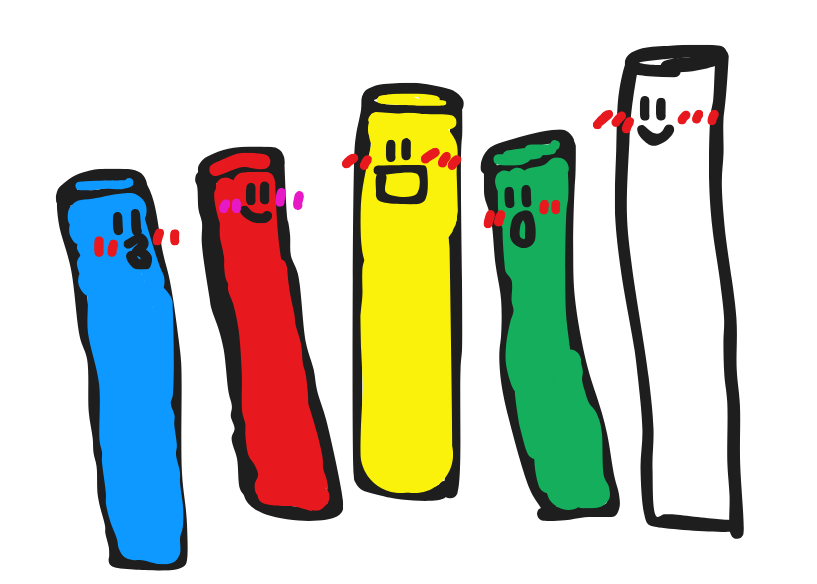

① チョークさんのつぶやき:「新採のころは、毎月168時間残業してたんです…」
🟢 チョークさん:「あの頃は本当に寝る間もなかったなあ…。平日120時間の時間外勤務に、土日はテストづくりで追加12時間ずつ。
つまり、合計168時間。今思えば、若さと根性で乗り切ってたようなもんですね。」
🟣 通帳さん:「ひぇぇ…。それ、完全に“二人分働いてる”レベルじゃないですか? でも、それだけ仕事があったってこと?」
🟢 チョークさん:「そうなんです。授業づくりもテストも、生徒指導も全部ひとりで抱えてました。最近は『スタディーエイド』っていうアプリで少しは楽になりましたけど。」
🟣 通帳さん:「なるほど、テクノロジーで少しずつ改善はしてるんですね。でも、まだ“多忙”って感じるんですよね?」
🟢 チョークさん:「そうなんです。働き方改革は進んできたけど、現場の空気はまだピリピリしてます。」
② 通帳さんの疑問:「じゃあ、なんでそんなに忙しいの?」
🟢 チョークさん:「理由は3つあります。」
1. ベテラン教員の減少と中堅層の薄さ
🟢 チョークさん:「私の学校、50代の先生がどんどん退職していって…。そのポジションを引き継ぐ中堅の先生が少ないんです。」
🟣 通帳さん:「じゃあ若手に仕事が集中するんですね?」
🟢 チョークさん:「そう。授業、生徒指導、校務…17時を過ぎてやっと自分の仕事ができる日も多いです。」
🟣 通帳さん:「なるほど。人員配置の問題、つまり“構造的な人手不足”ってわけですね。」
2. 生徒一人ひとりの個性を尊重する文化
🟢 チョークさん:「今は“多様性を認める教育”が大事にされています。もちろん大賛成なんですが…」
🟣 通帳さん:「その“もちろん”のあとに“でも”が来るパターンですね。」
🟢 チョークさん:「はい(笑)。個別対応が増えて、指導方針を一本化できない。落ち着きのない子、控えめな子、主張の強い子…。それぞれに合わせようとすると、時間も労力もかかります。」
🟣 通帳さん:「なるほど。『個性の尊重=対応の複雑化』というジレンマですね。」
3. 委員会・研究会などの外部業務の増加
🟢 チョークさん:「あと、自治体の研究会とか委員会も多いんです。発表や資料づくり、出張…。もちろん学びの機会なんですけどね。」
🟣 通帳さん:「出張も仕事ですもんね。時間は有限なのに、やることが増えていくと…。」
🟢 チョークさん:「そうなんです。出張から戻って夜遅くまで学校で仕事をしてる先生もいます。『バランスを取って』って言われても、業務そのものが多すぎて難しいんですよ。」
🟣 通帳さん:「なるほど…。制度より先に“現場の時間”が限界なんですね。」
③ チョークさんの結論:「結局、教員を増やすしかないんです!」
🟢 チョークさん:「いくら工夫しても、人が足りないと限界です。教員を増やして、待遇を改善して、“続けたい仕事”にしてほしいです。」
🟣 通帳さん:「“教育への投資”って、子どもたちだけじゃなく先生たちにも必要なんですね。」
🟢 チョークさん:「その通り! 教員を増やすことは、未来への一番確かな投資です!」
🟣 通帳さん:「今日の話、すごく勉強になりました。チョークさん、今度スタディーエイドの紹介もしてくださいね!」
🟢 チョークさん:「もちろん! じゃあ次回は“テストづくりが一日で終わる秘密”について話しましょうか。」
💡まとめ:「多忙化を止めるには、仕組みよりまず“人”を」
教員の働き方改革は、現場の努力だけでは限界があります。
人を増やし、時間を取り戻すことができてこそ、子どもたちに本当に向き合える環境が整います。
今日も、チョークさんと通帳さんはそんな未来を夢見て、静かな放課後を過ごしているのでした。