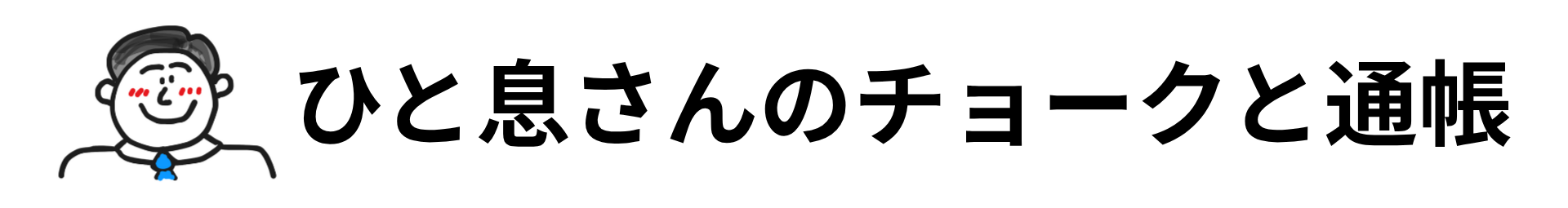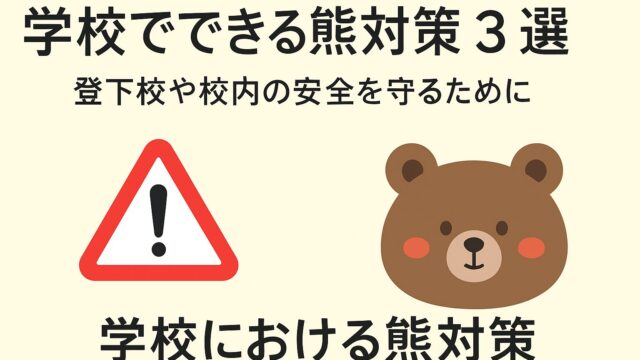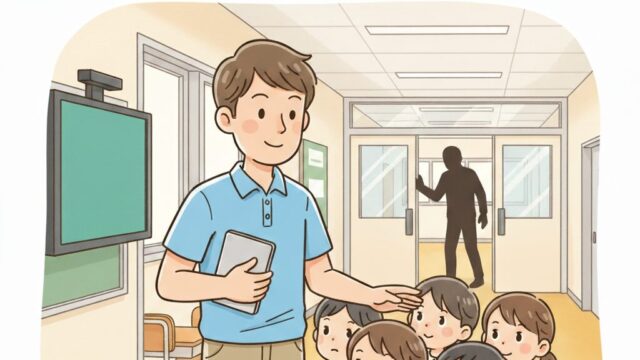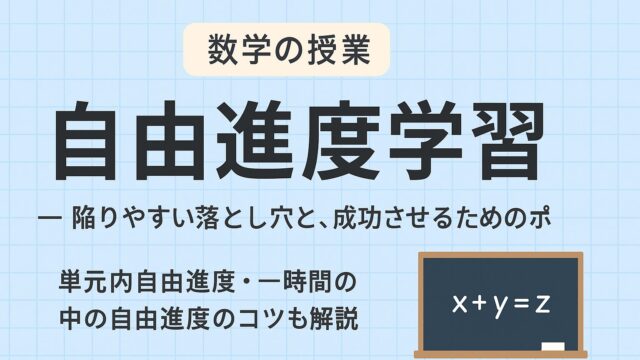学校現場で子どもを守るために|教員としてできる性被害防止の取り組み

【教員必読】性犯罪から生徒を守るために大切な3つの視点
近年、教員による性犯罪や不適切な関わりが社会問題となり、教育現場の信頼が揺らぐ事例も見られます。
一方で、多くの教員が「子どもを守りたい」という思いを持ちながら誠実に働いているのも事実です。
この記事では、「子どもを守る」「信頼を守る」ために教員が意識すべき3つの視点を紹介します。
Contents
1. 学校全体でのルールと体制を整える
性被害を防ぐには、個人の意識だけでなく学校全体の体制づくりが欠かせません。
- 更衣室・保健室・相談室のドアは施錠・透明化(プライバシーを守りつつ見守り可能に)
- 1対1の場面をできるだけ避ける(複数の教員やオープンスペースで対応)
- 保護者・同僚との情報共有(「見える関係」「透明な対応」を意識)
「物理的・制度的に防ぐ仕組み」を整えることで、リスクを大幅に減らせます。
2. 教員自身が「境界線」を意識する
子どもとの信頼関係を築くことは大切ですが、「距離感を保つプロ意識」も同じくらい重要です。
境界線を守るポイント
- LINEなど個人SNSではなく、学校の公式アカウントでやりとり
- 必要以上の身体的接触は避ける(ハイタッチも慎重に)
- 放課後・休日の私的な接触は持たない
「信頼関係」と「私的関係」は違います。
教師としての立場を意識した言動を続けることが、子どもと自分を守る最善の方法です。
3. 被害を防ぐ教育・相談体制を整える
子ども自身が性被害を防ぐための教育も重要です。
文部科学省のガイドラインでは、性教育・人権教育の一環として「性暴力防止教育」を進めることが推奨されています。
学校でできる取り組み例
- 「いや」と言える練習、助けを求める方法を教える
- 性や人権に関する授業で、安全な関係性を考える
- 相談窓口(スクールカウンセラー・外部支援)の掲示
生徒が安心して声を上げられる環境づくりが、最大の予防策になります。
まとめ:信頼を守ることが、子どもを守ること
教員は、子どもにとって「社会の安全の象徴」であり、「信頼の存在」です。
一人ひとりが意識と行動を変えることで、被害も加害も防ぐことができます。
「誤解を招かない関わり」「透明性のある指導」「チームでの対応」。
この3つを意識して、安心できる学校づくりを進めていきましょう。